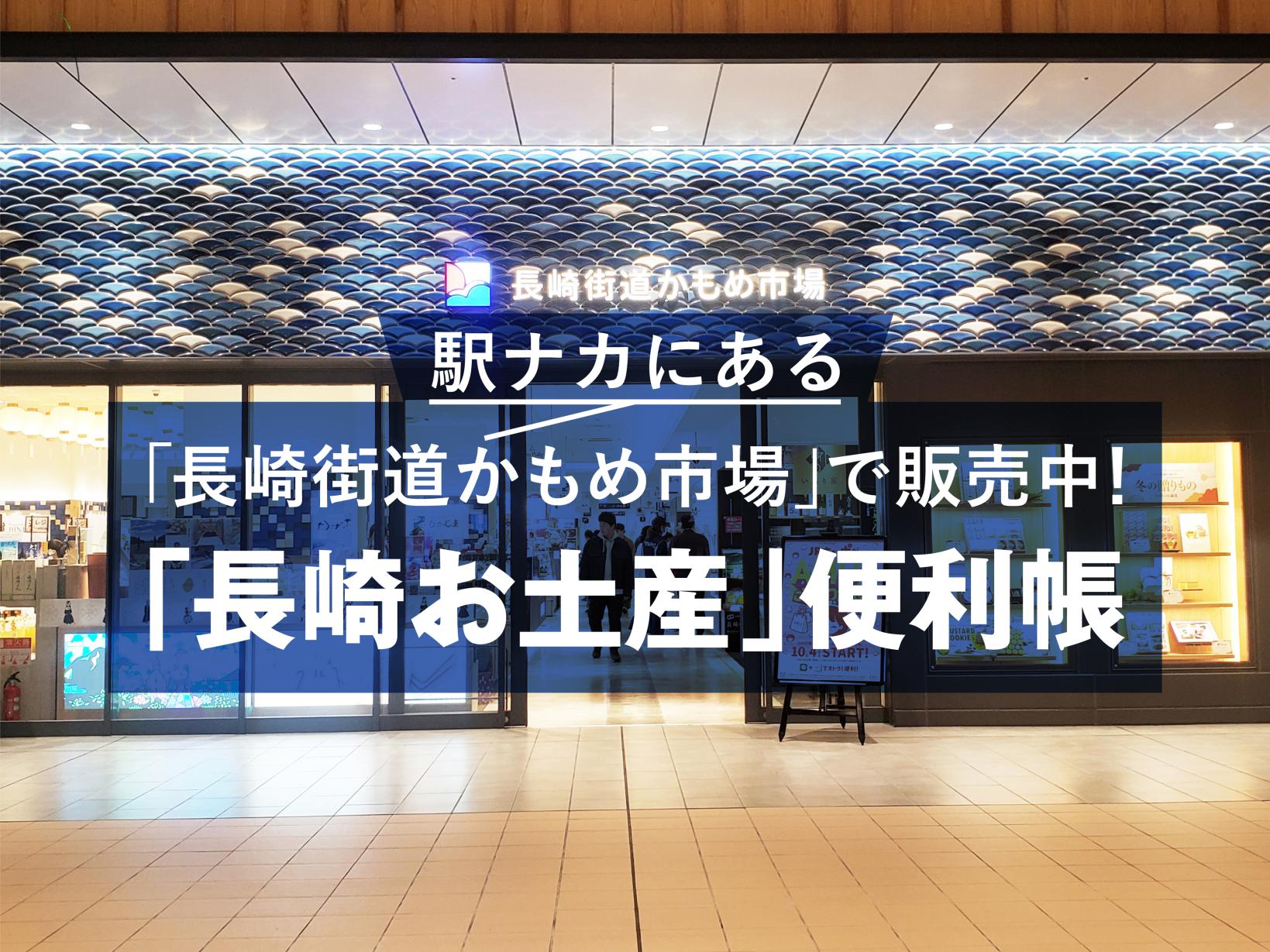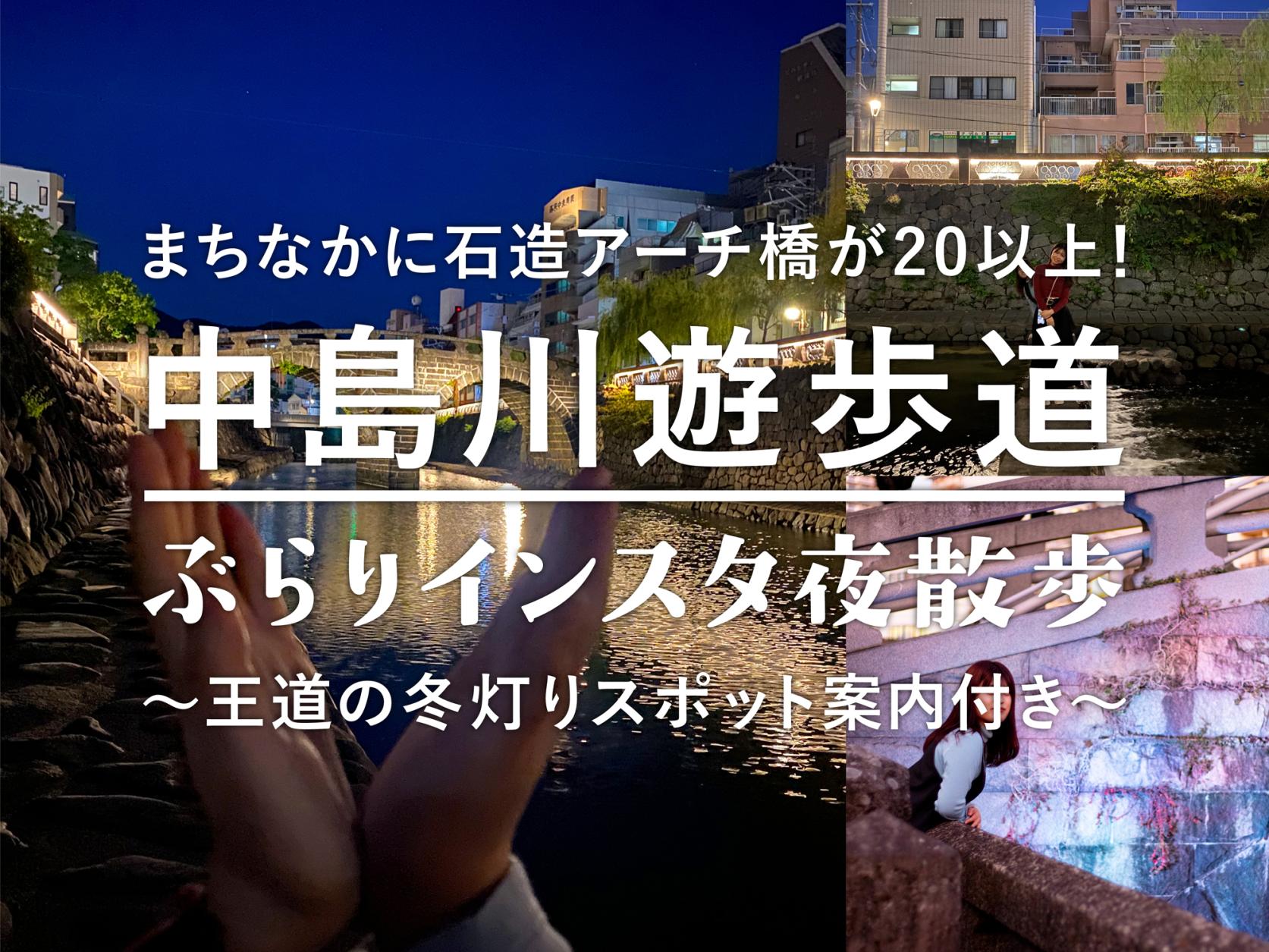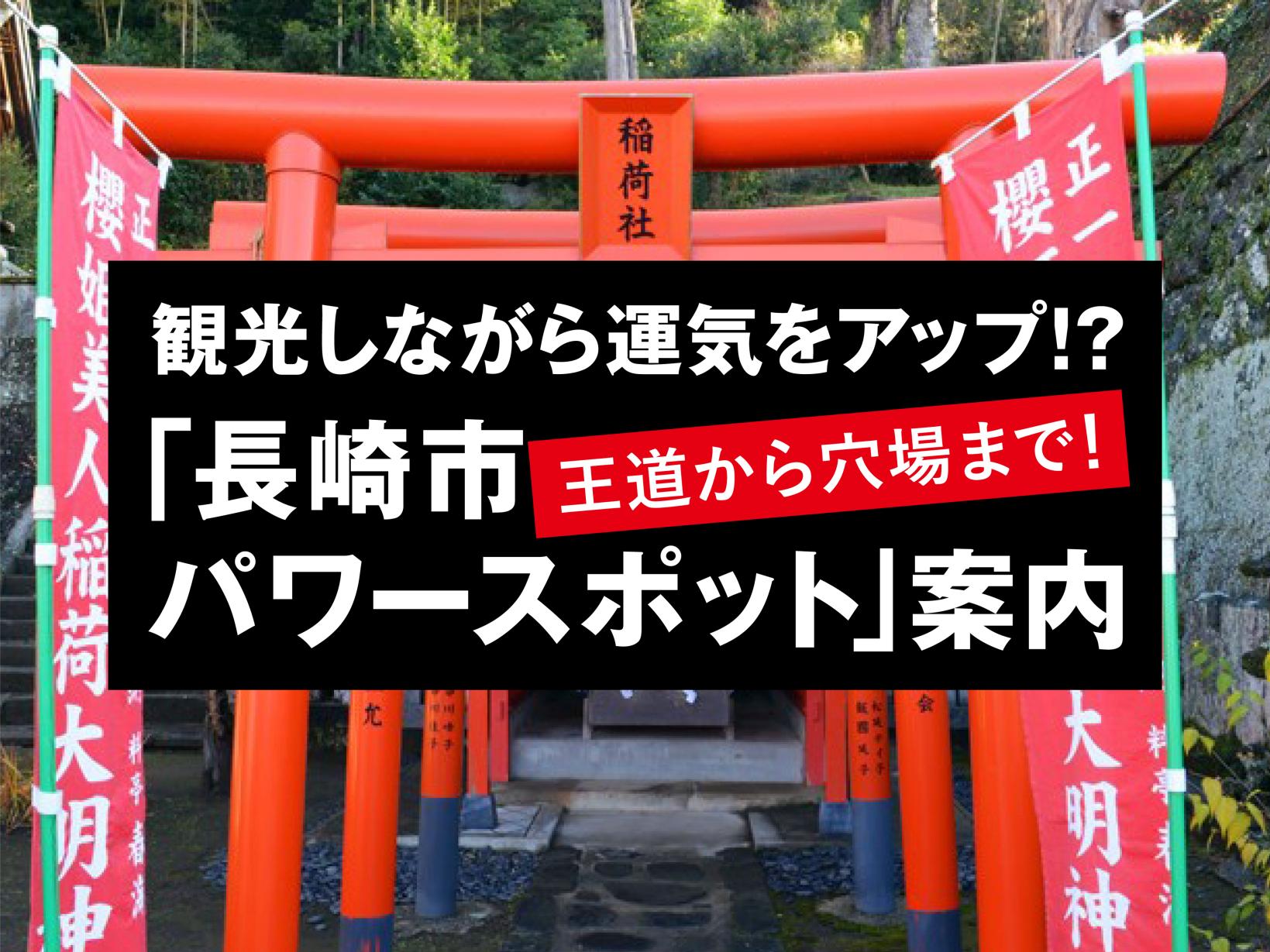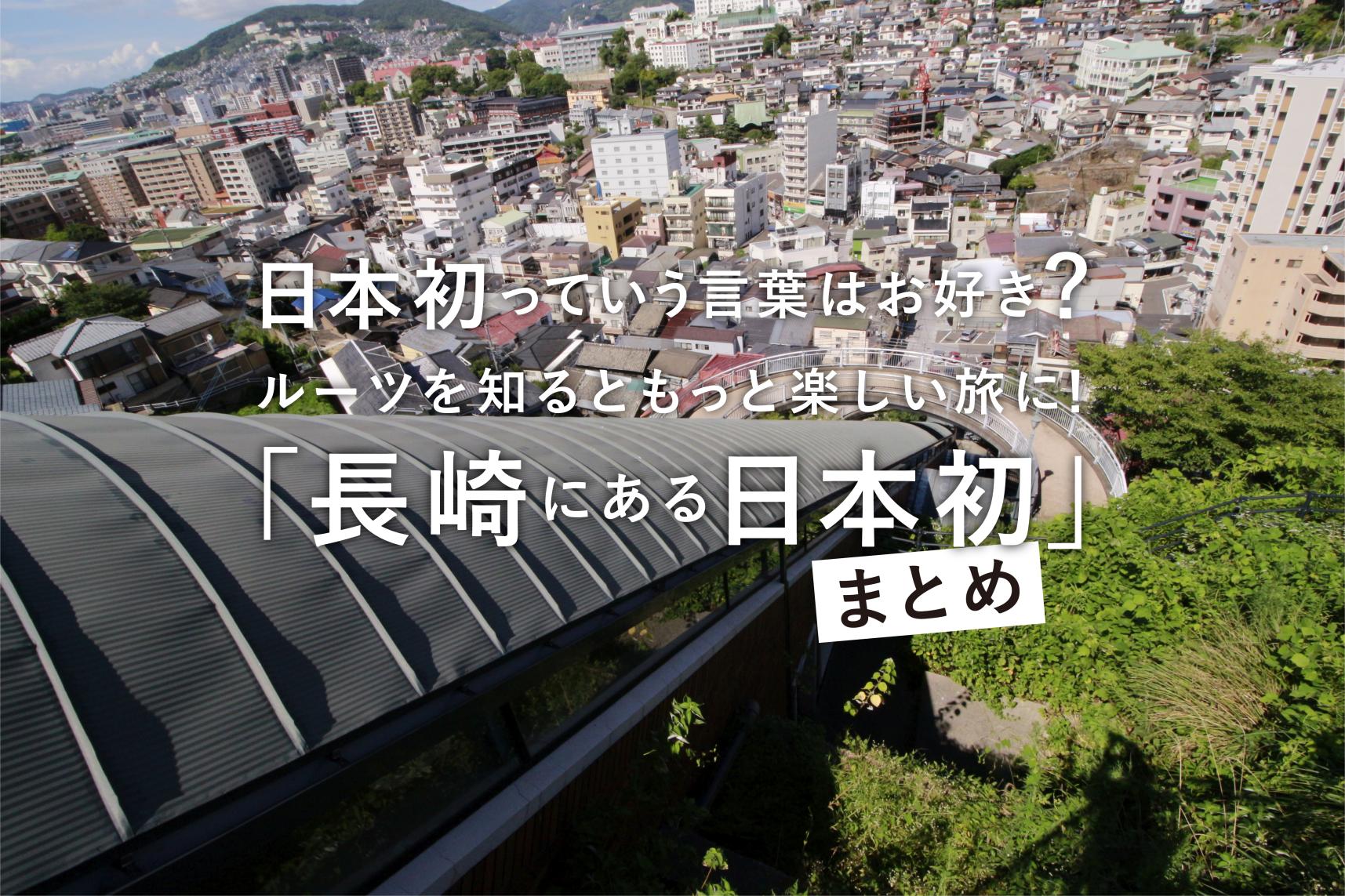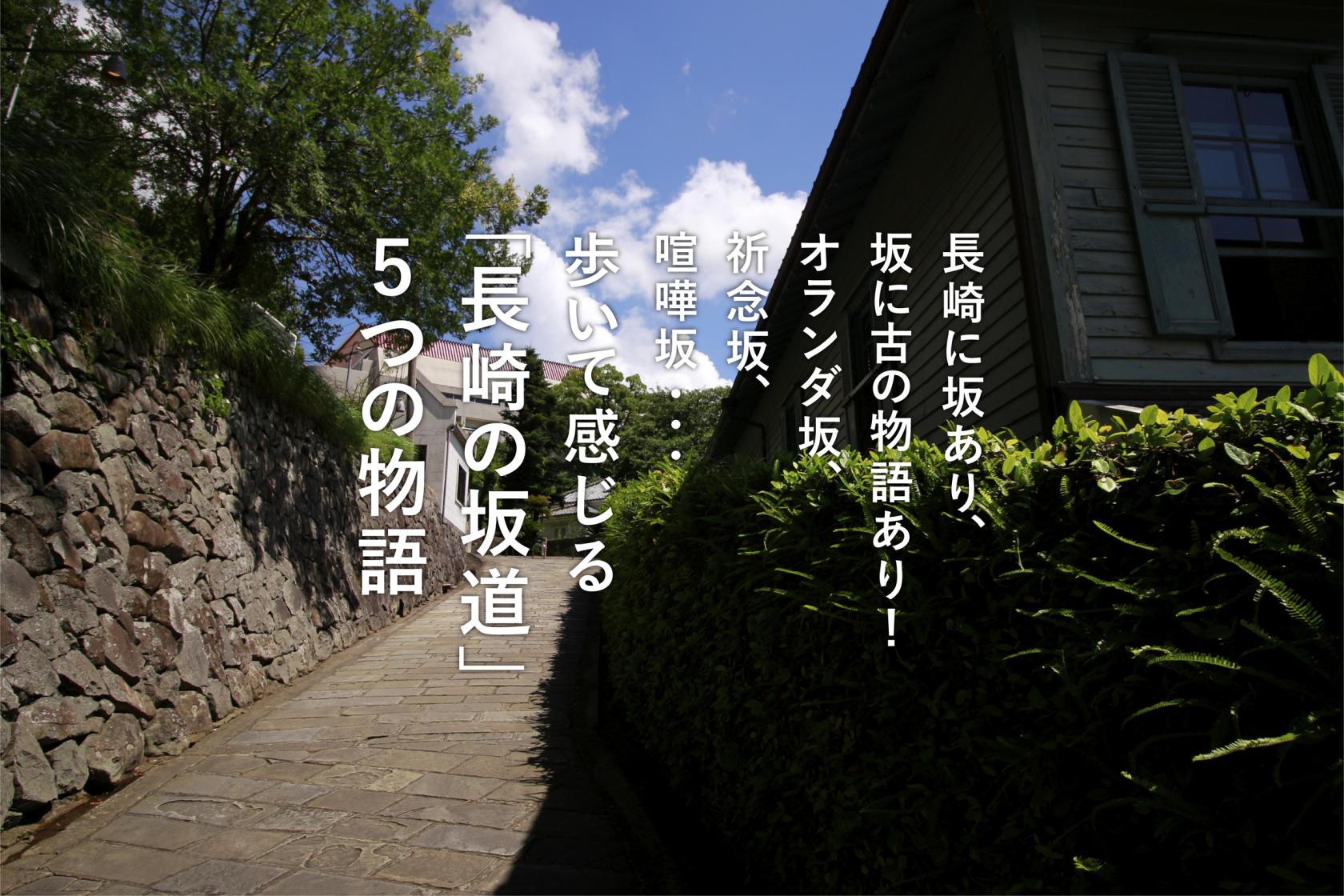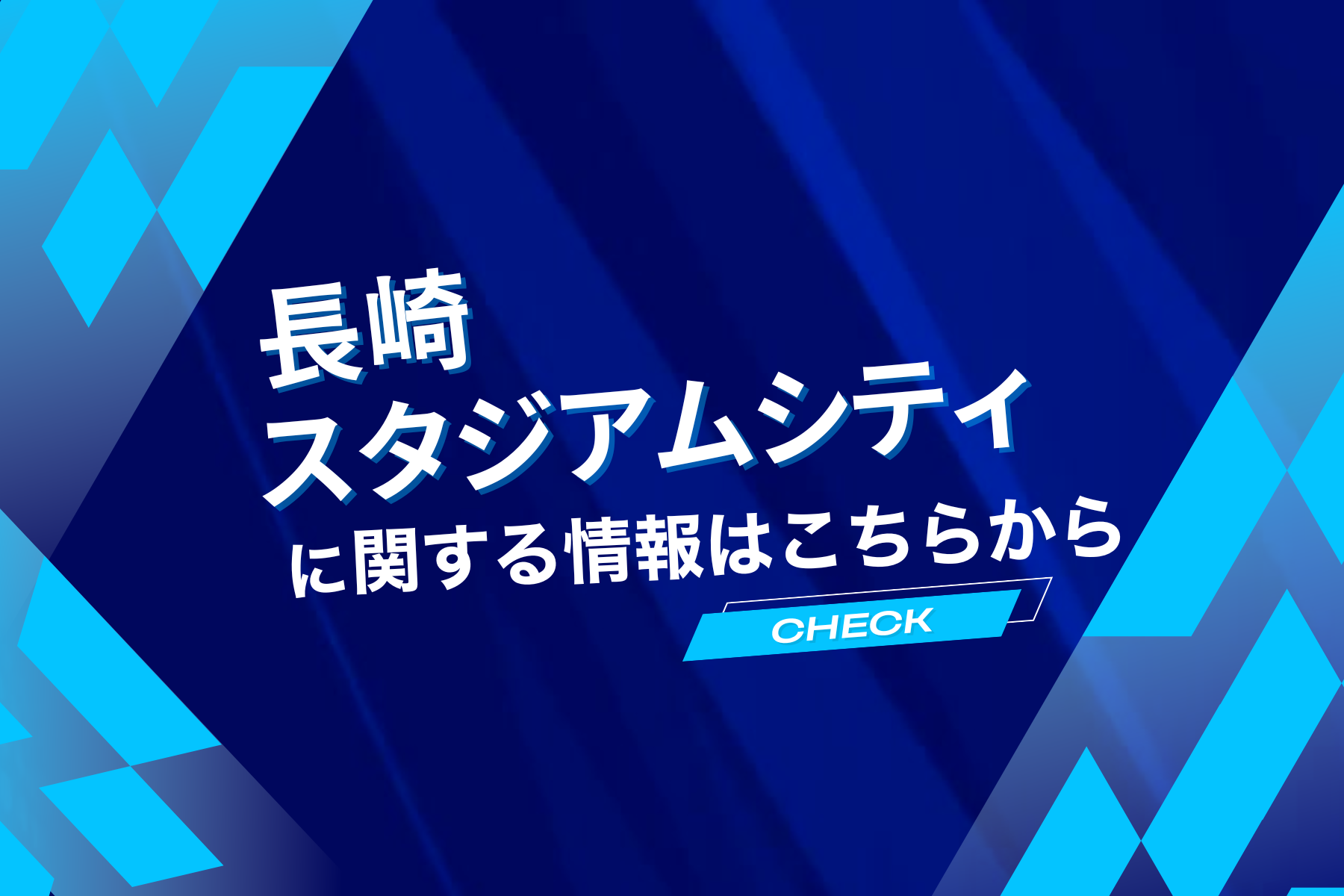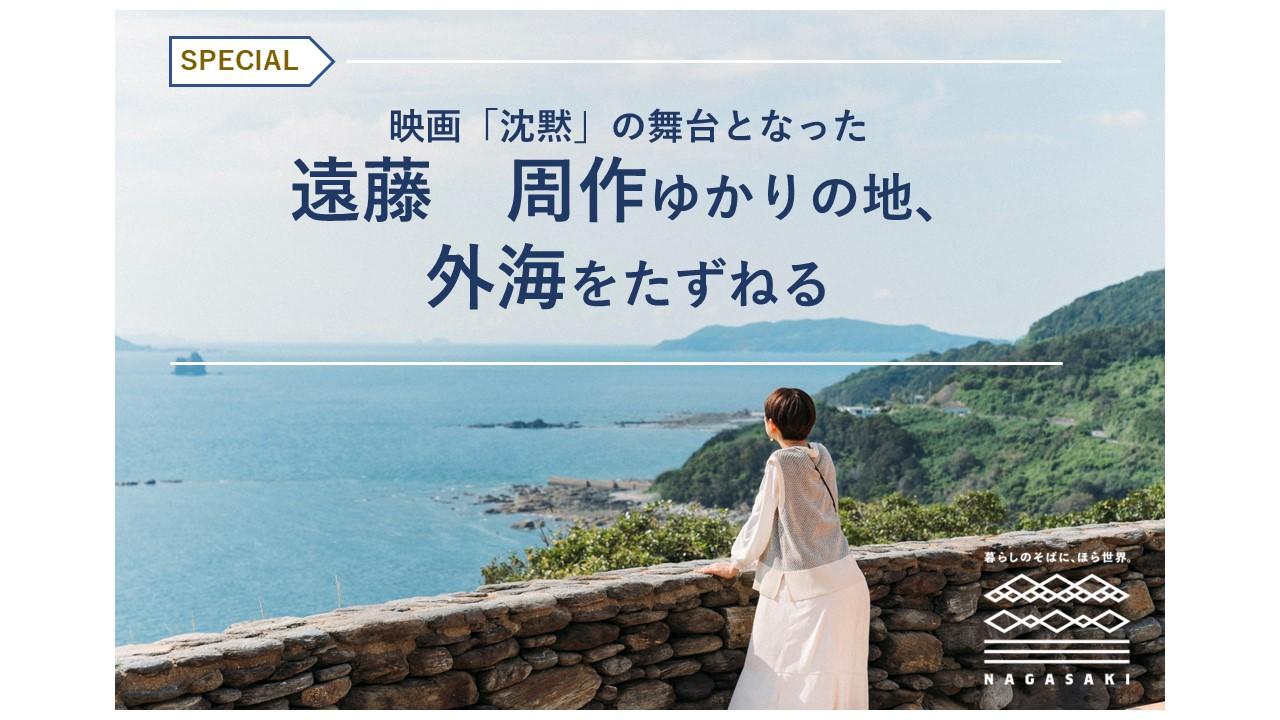#004 ながさきとくんち
#004 ながさきとくんち
⻑崎くんちの後を賑わす 秋の⾵物詩、⽵ン芸。本ページでは、⽵ン芸の歴史⽂化のストーリーから、
イベント情報までご紹介します。
⻑崎随⼀のスリリングな祭り ⽵ン芸
【秋空にお囃⼦鳴り響く 若宮稲荷神社】
若宮稲荷神社は、町役⼈・若杉喜三太が1673 年、⾃邸に祀っていた稲荷⼤神を伊良林の地に移し、社殿を創建したことに始まるといわれています。その後多くの⼈から敬われ、1736年、⻑崎奉⾏の細井因幡守安明が新たに参道を開通し、神殿が改築されました。⽵ン芸は、毎年10⽉14 ⽇・15⽇の⼆⽇間、若宮稲荷神社の秋の例⼤祭に奉納される⾏事です。元々は⻑崎くんちの奉納踊りだったもので、戦後に復活したと⾔われています。稲荷神社の御使いである狐が若宮社の御神徳を慶んで、裏の⽵やぶで軽やかに遊ぶ姿を模したものと伝えられており、国の無形⺠俗⽂化財にも指定されています。
【アクロバティックに舞う ⼀対の稲荷狐】
笛と締太⿎、三味線のお囃⼦とともに、⾼さ約11mの⼀対の⻘⽵の上で、⽩装束に狐の⾯をかぶった雄狐と雌狐が、命綱をつけずに両⾜のみで⽵にぶら下がる「逆⽴ち」、⽚⽅の⽵に頭を、もう⽚⽅の⽵に⾜を引っかけた雄狐の⾝体に、雌狐が両⾜でぶら下がる合わせ技「⾕のぞき」などのアクロバティックな曲芸を次々と⾏う姿はまさに圧巻。頂上に座った雄狐が⼤きく⽵を揺らして観客の⽬が釘付けになったところで、懐から取り出すのは⼿拭いや紅⽩の餅などの縁起物。それらを観客に向けてばらまき、クライマックスにはサラシで包まれた狐の好物・⽣きた鶏を空に放ち、幸運な観客の⼿に渡ります。すっかり⾝軽になった雄狐は⼤技を披露した後に、⾜だけを⽵に絡ませながら⼀気に滑り落ちると、途端に会場の緊張感が解けて拍⼿喝采となるのです。
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)