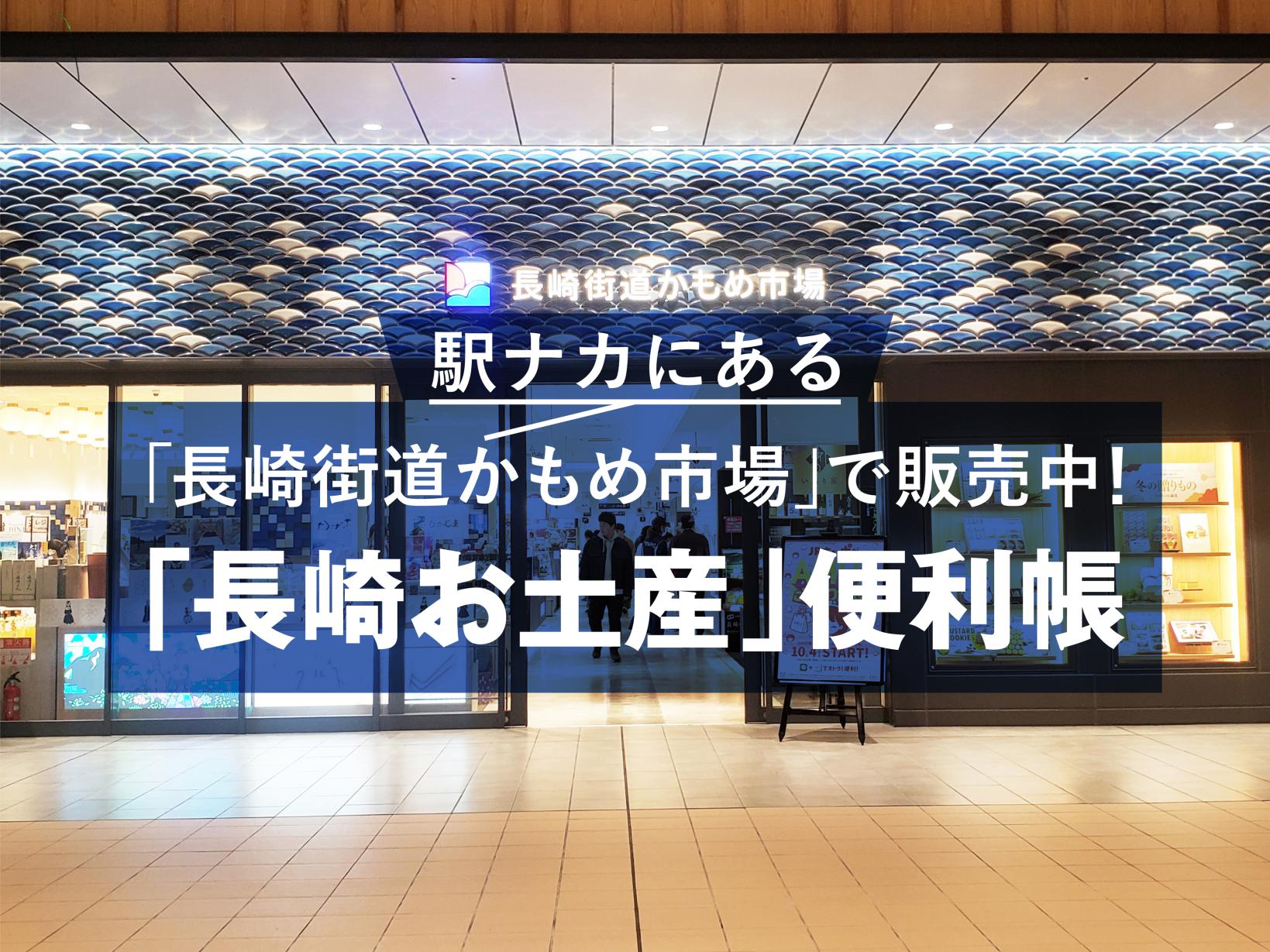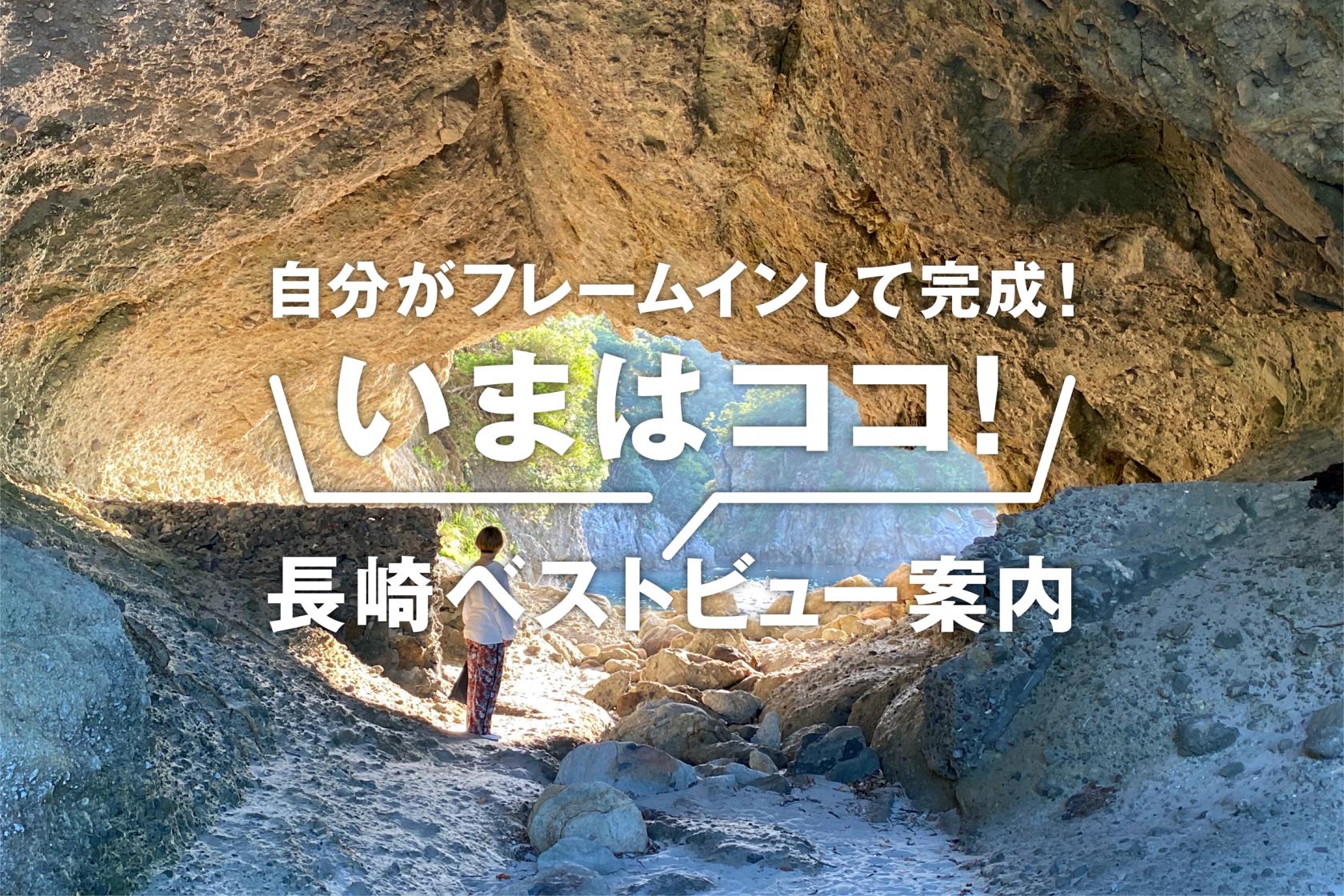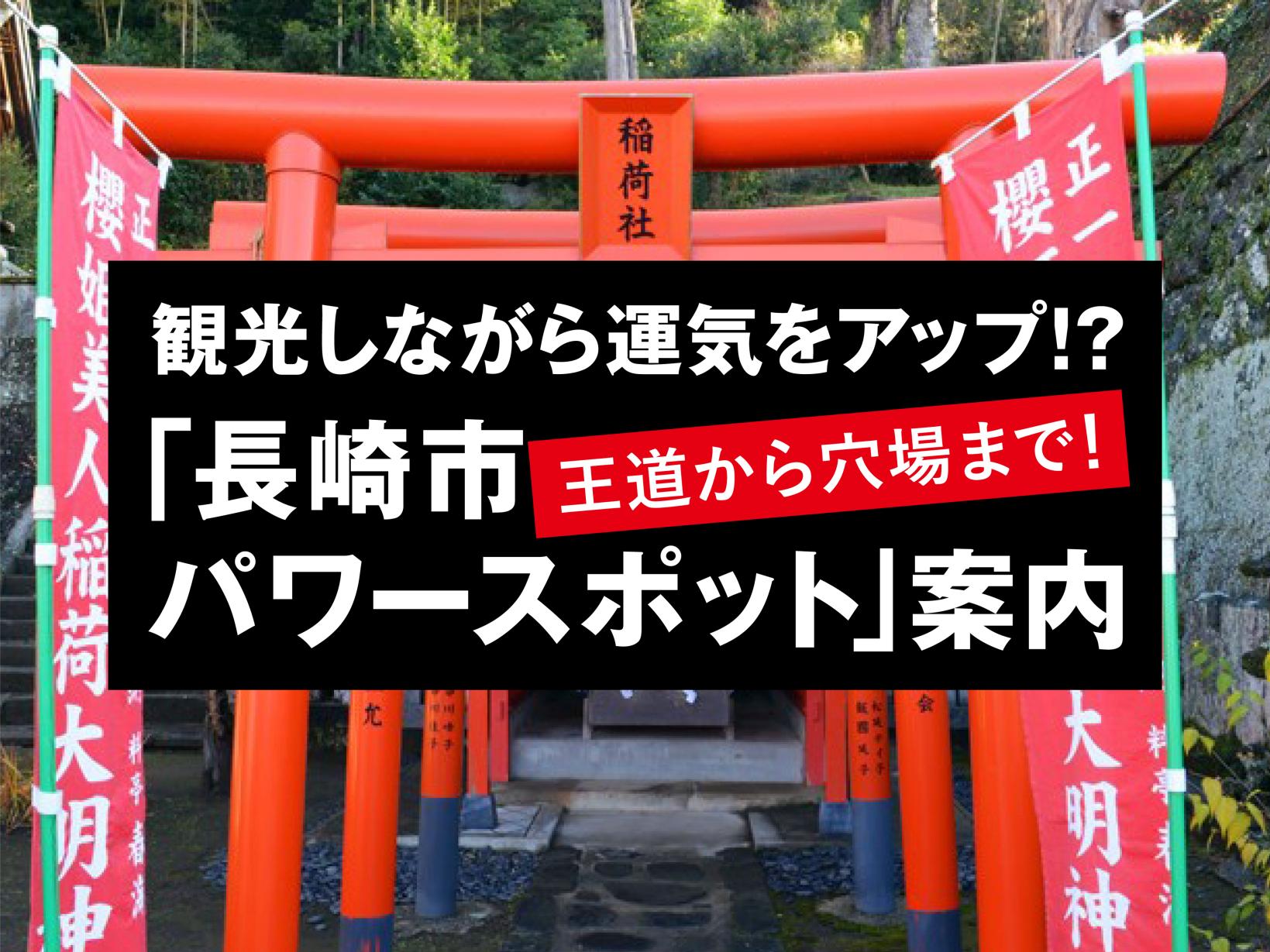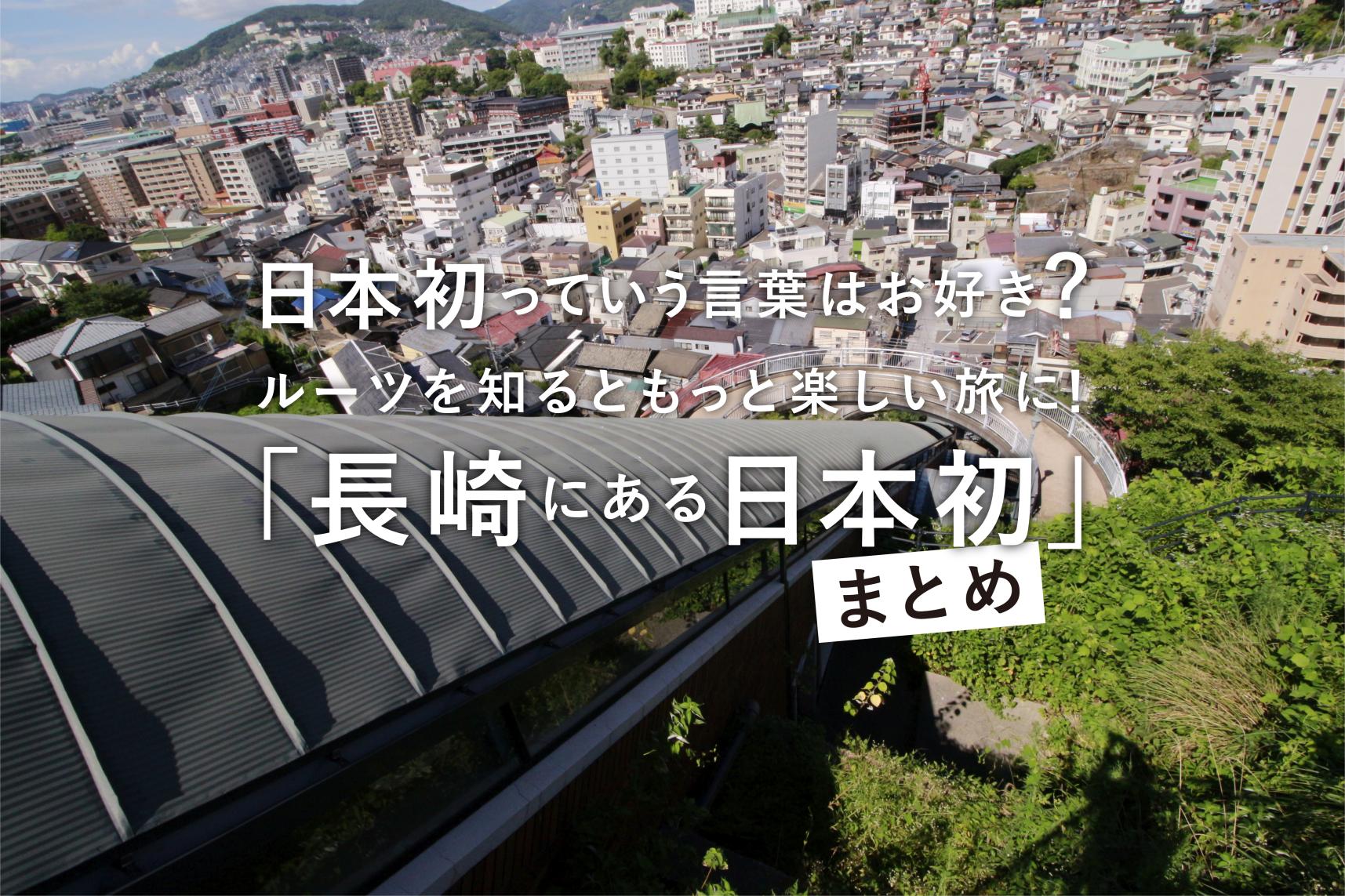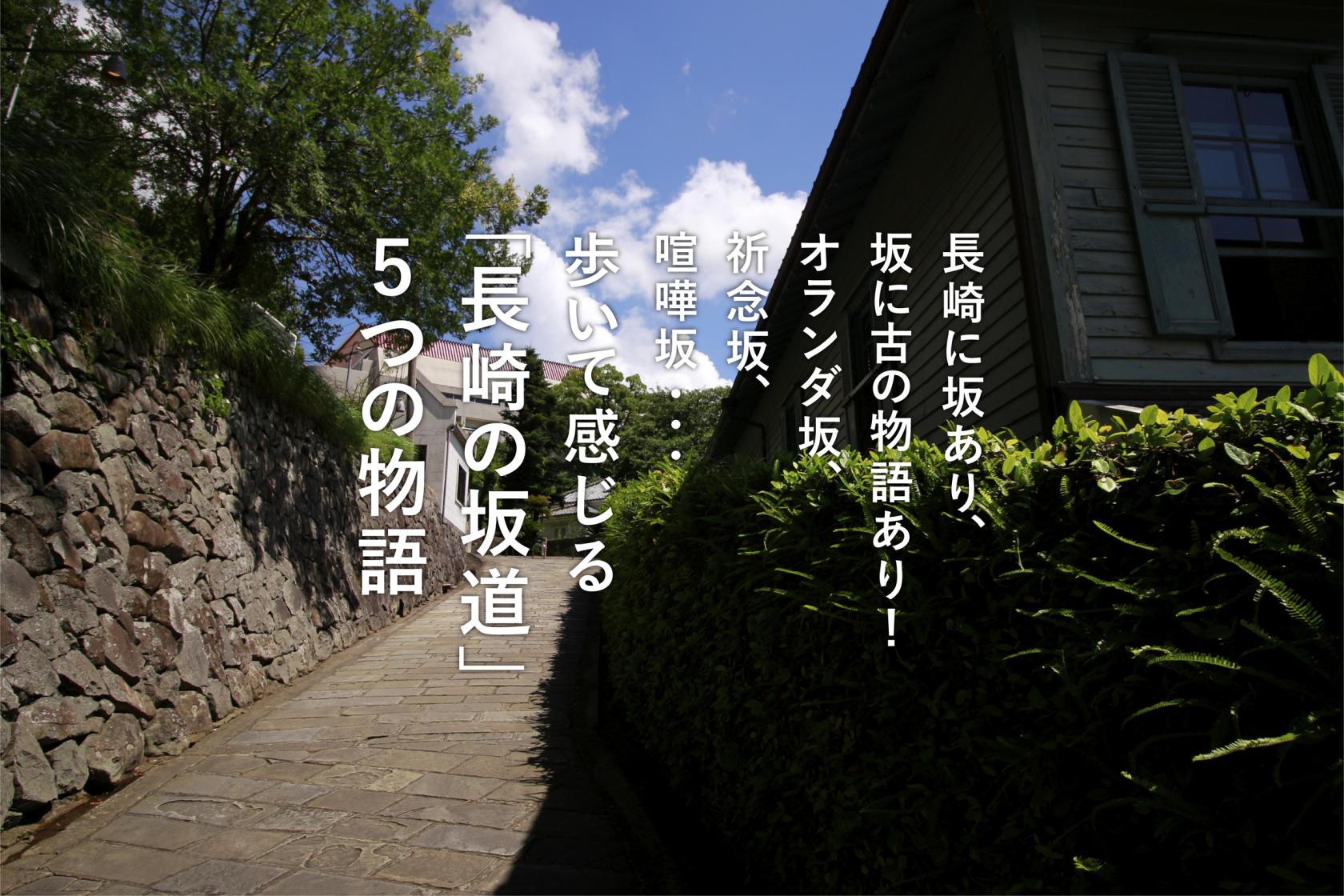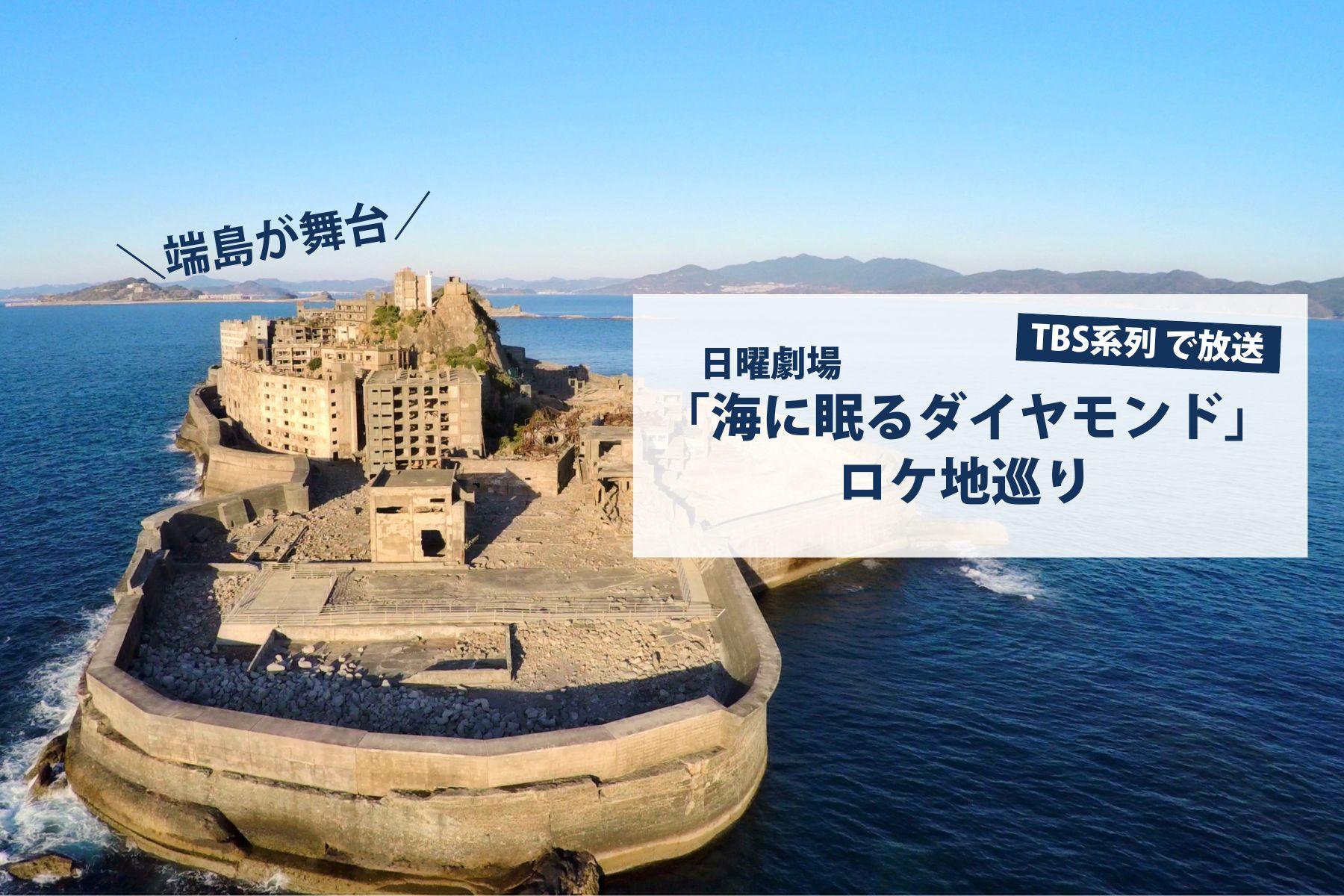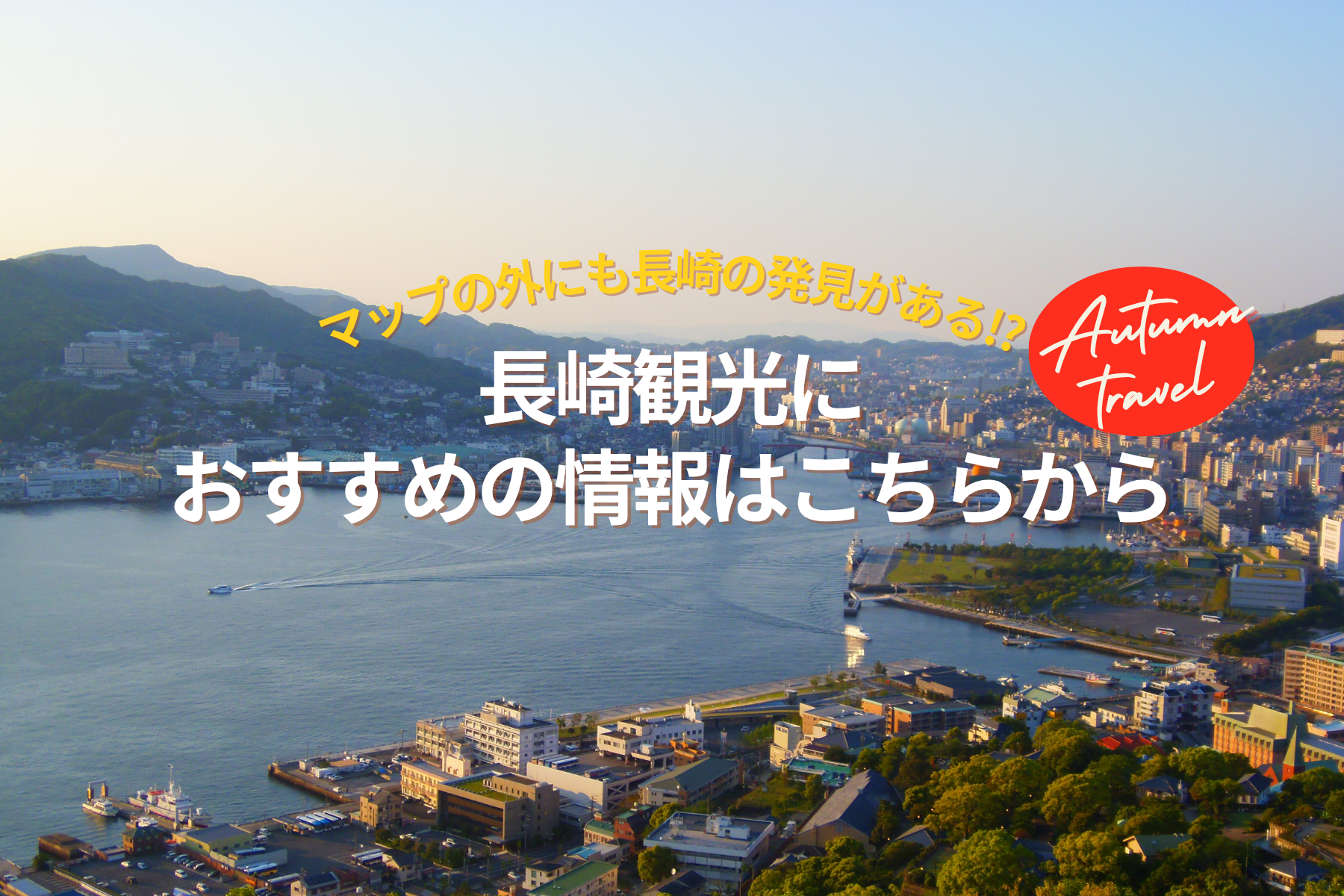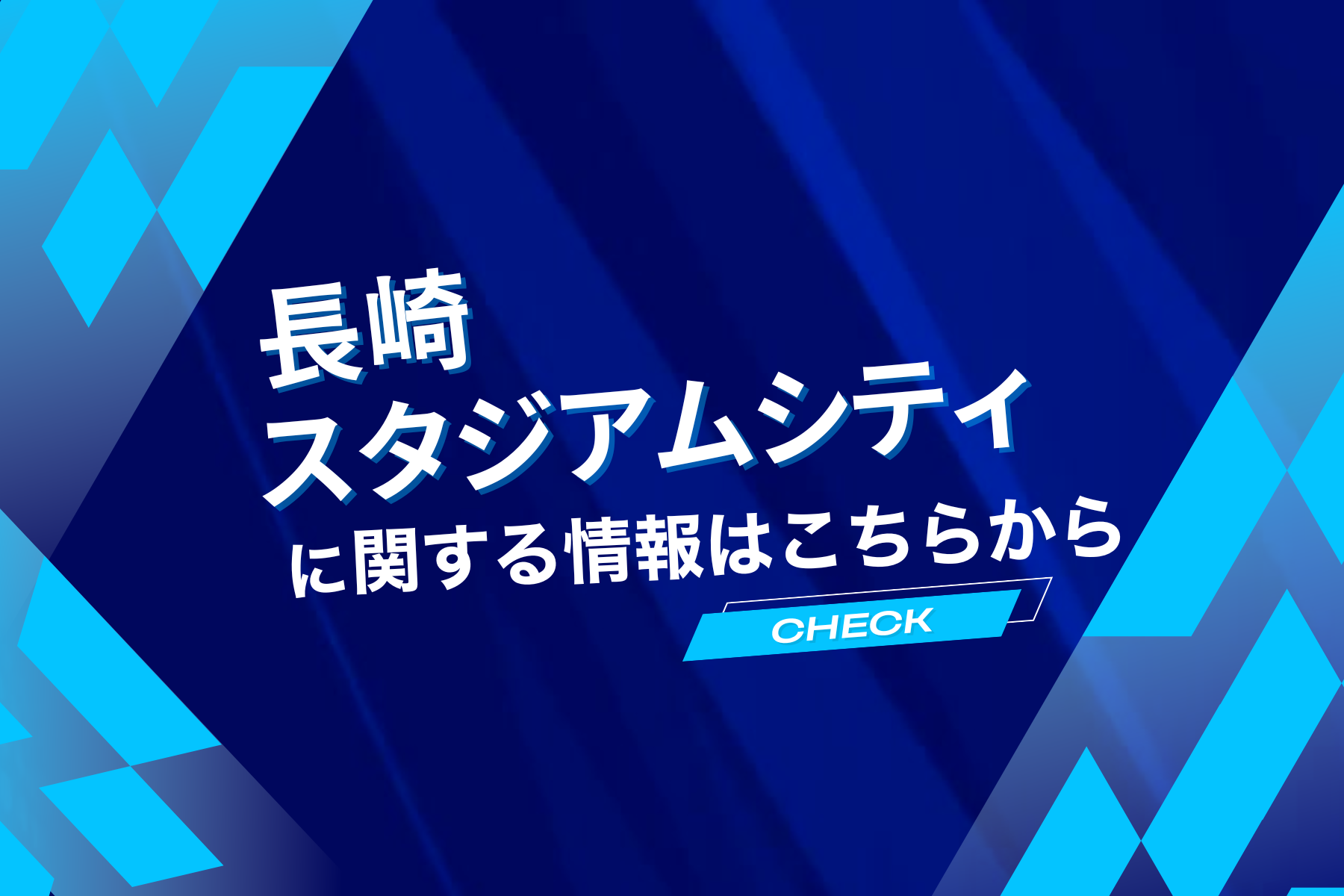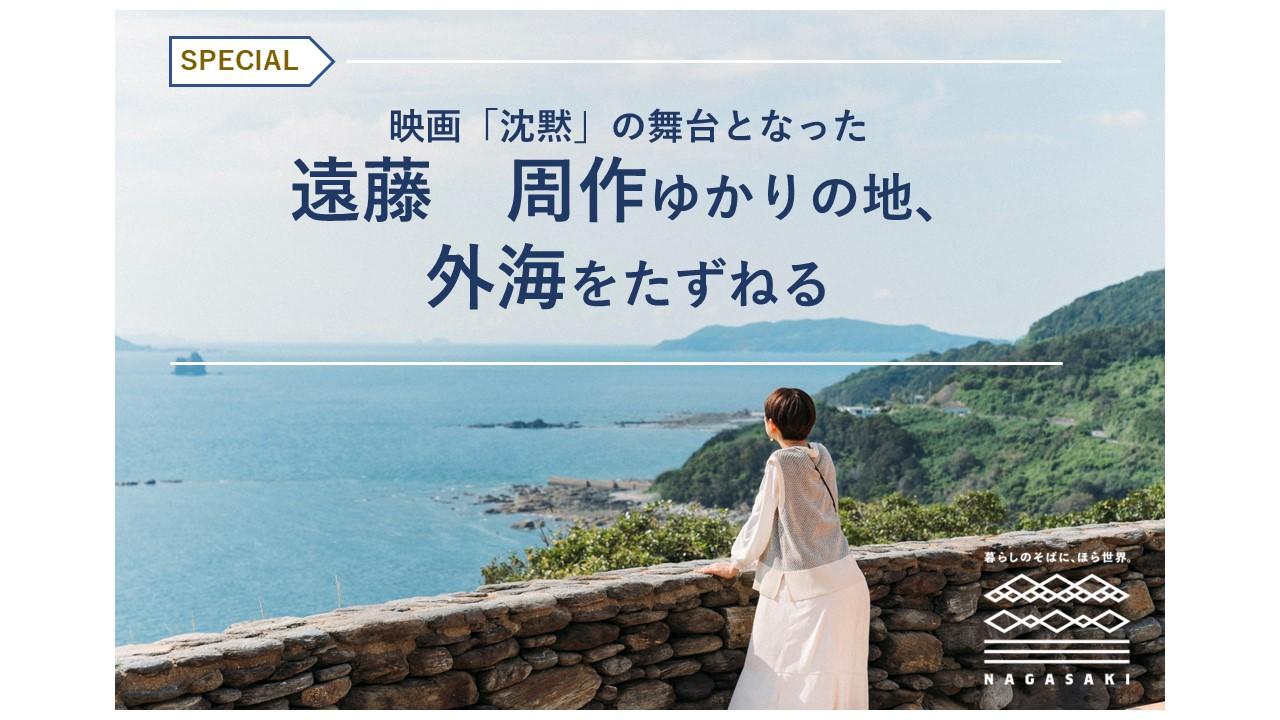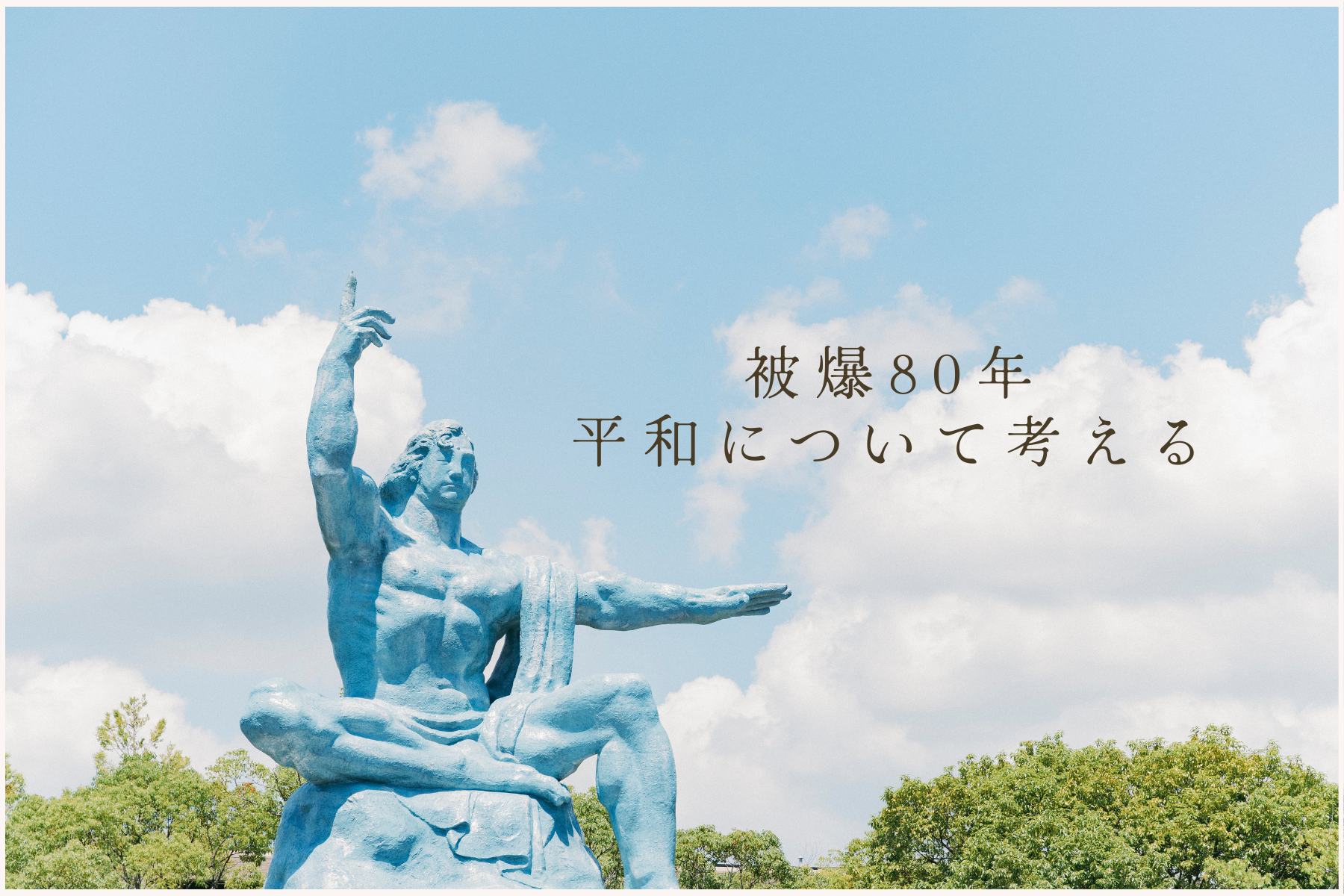#003 ながさきと中国文化
#003 ながさきと中国文化
いわゆる鎖国の時代、唯一中国との貿易港だった長崎には唐人屋敷がありました。本ページでは、長崎の中国文化をたどるストーリーから、長崎を代表する中華グルメまでご紹介します。
日本最古のチャイナタウン
【中国文化 唐人屋敷】
いわゆる鎖国政策下の長崎は、日本における唯一の幕府直轄の国際貿易港でした。西洋との貿易窓口「出島」と同様に重要な役割を果たしていたのが、東洋との貿易窓口「新地蔵」。1689年、幕府は密貿易を取り締まるため、それまでまちなかの馴染みの家などに泊まっていた中国人たちを一か所に滞在させる唐人屋敷をつくりました。周囲を堀などで囲まれた場所で、中国人たちは、故郷と同じように伝統行事を行いながら、帰港の日まで過ごしました。唐人屋敷内にある土神堂前の広場では、長崎くんちにも登場する「龍踊」の演舞や、月琴(げっきん)、笛、銅鑼(どら)、喇叭(らっぱ)などの楽器の演奏にあわせて役者が演技をする「唐人踊」などの様々な行事が行われ、長崎の様々な文化に大きな影響を与えました。
【倉庫からグルメタウンへ 長崎新地中華街】
横浜、神戸と並ぶ三大中華街の中で、最も古い歴史を持つ長崎新地中華街。この場所は元々、江戸時代に中国貿易の品物を保管するために、海面約3,500坪を埋め立て造成された倉庫 新地蔵所でした。幕府の開港後、港に程近い新地蔵所跡地に、徐々に中国人たちが移り住み商いを始めたことで、ちゃんぽん・皿うどんなどの中華料理や中華菓子、中国雑貨店で賑わう、現在のグルメタウン 長崎新地中華街が徐々に形成されていきました。
長崎中華のエッセンス 厳選グルメ・お土産
【長崎の大定番「ちゃんぽん・皿うどん」】
今や長崎グルメの代名詞として全国に広まっている「ちゃんぽん・皿うどん」。1899年、中華料理店 四海樓の店主・陳平順氏が、貧しい中国人留学生に安くて栄養があるものをふるまうために最初に考案されたのが「ちゃんぽん」。続いて、平皿にのった汁なしちゃんぽんとして考案されたのが「皿うどん」。一つの中華鍋で、野菜・肉・海鮮・かまぼこを一気に炒めて、ぐっと旨味を煮込んだ贅沢なスープとあんかけが絡むボリュームたっぷりの絶品麺料理は、今もなお長崎人からこよなく愛されています。皿うどんは、ちゃんぽん麺を使った「太麺」、パリパリに揚げた「細麺」の2種類からお好みで選んで、食事の途中でウスターソースをかけて味変を楽しむのも定番です。
【ほろりとろける「角煮まんじゅう」】
長崎和華蘭料理のフルコース、卓袱料理の中鉢に提供されるメインディッシュで、豚のバラ肉を砂糖と醤油で甘辛く煮た角煮「東坡煮(トンポーロー)」。これをワンハンドで気軽に食べられるように生まれたのが「角煮まんじゅう」です。ふわっとした生地にトロトロの角煮をはさんだ中華まんは、食べ歩きやお土産にも大人気です。
【硬くて素朴な揚げ菓子「よりより」】
江戸時代、中国から麻の花に似るとされた「麻花兒(マファール)」という名で伝来したと言われており、長崎では螺旋状に編まれた特徴的な形状から、「よりより」という愛らしい名称で親しまれています。カリッと音が鳴るほどの硬い食感が一番の特徴で、噛むほどに奥深い甘味が広がり、一度食べたら癖になる素朴でやさしい揚げ菓子です。
【家族円満を願う「月餅」】
古代中国に起源を持つ中華菓子で、江戸時代に長崎に伝わったと言われています。中国では、旧暦の8月15日の中秋節には、家族や親しい友人が集まり、月を愛でて月餅を食べる風習があります。小麦粉の生地に、くるみなどの滋養豊かな木の実を混ぜ合わせた餡に包んで焼き上げます。木の実の風味や食感の良い上品な味わいで、伝統菓子らしい文様にも各店舗が趣向を凝らしています。
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)