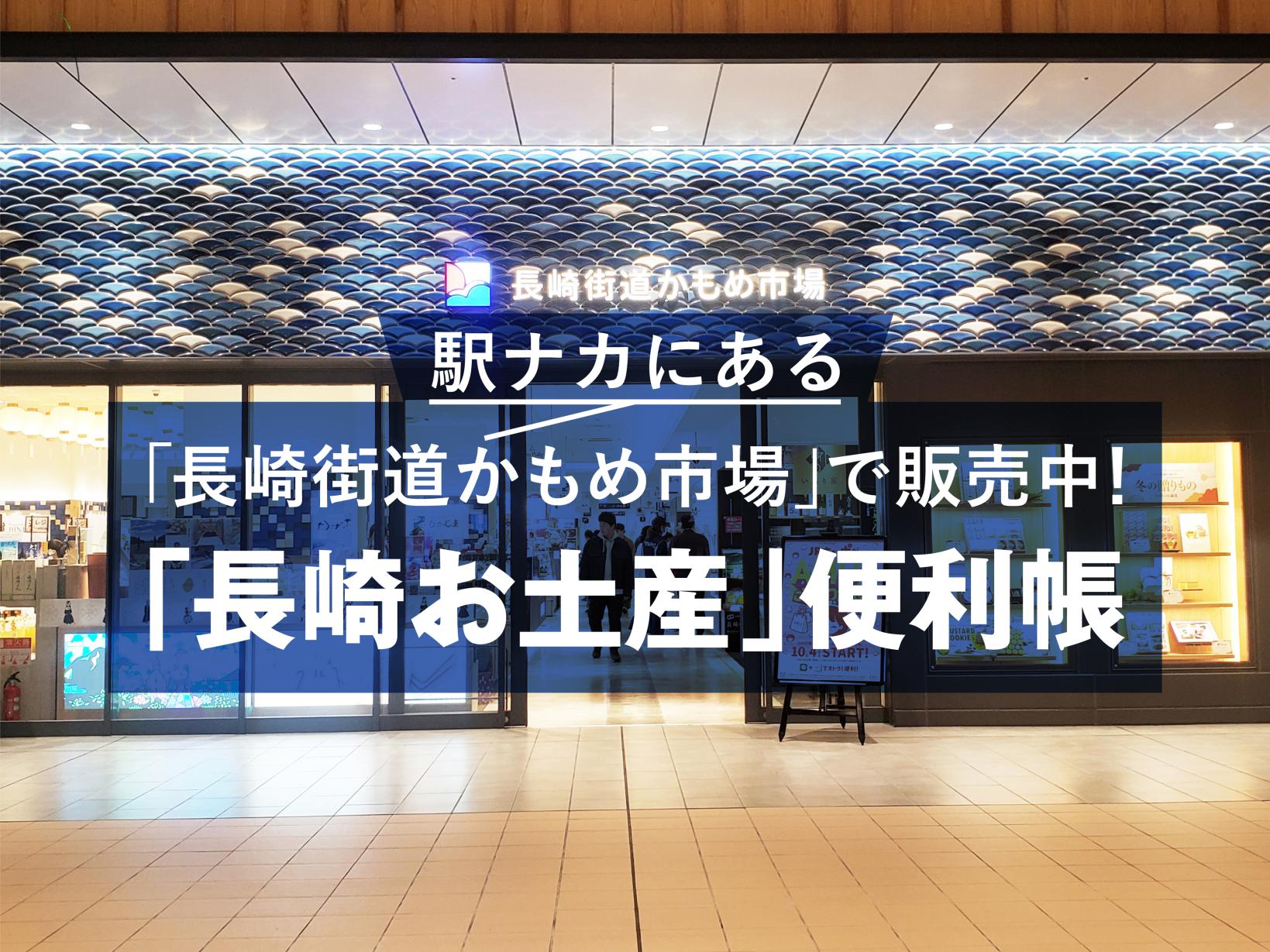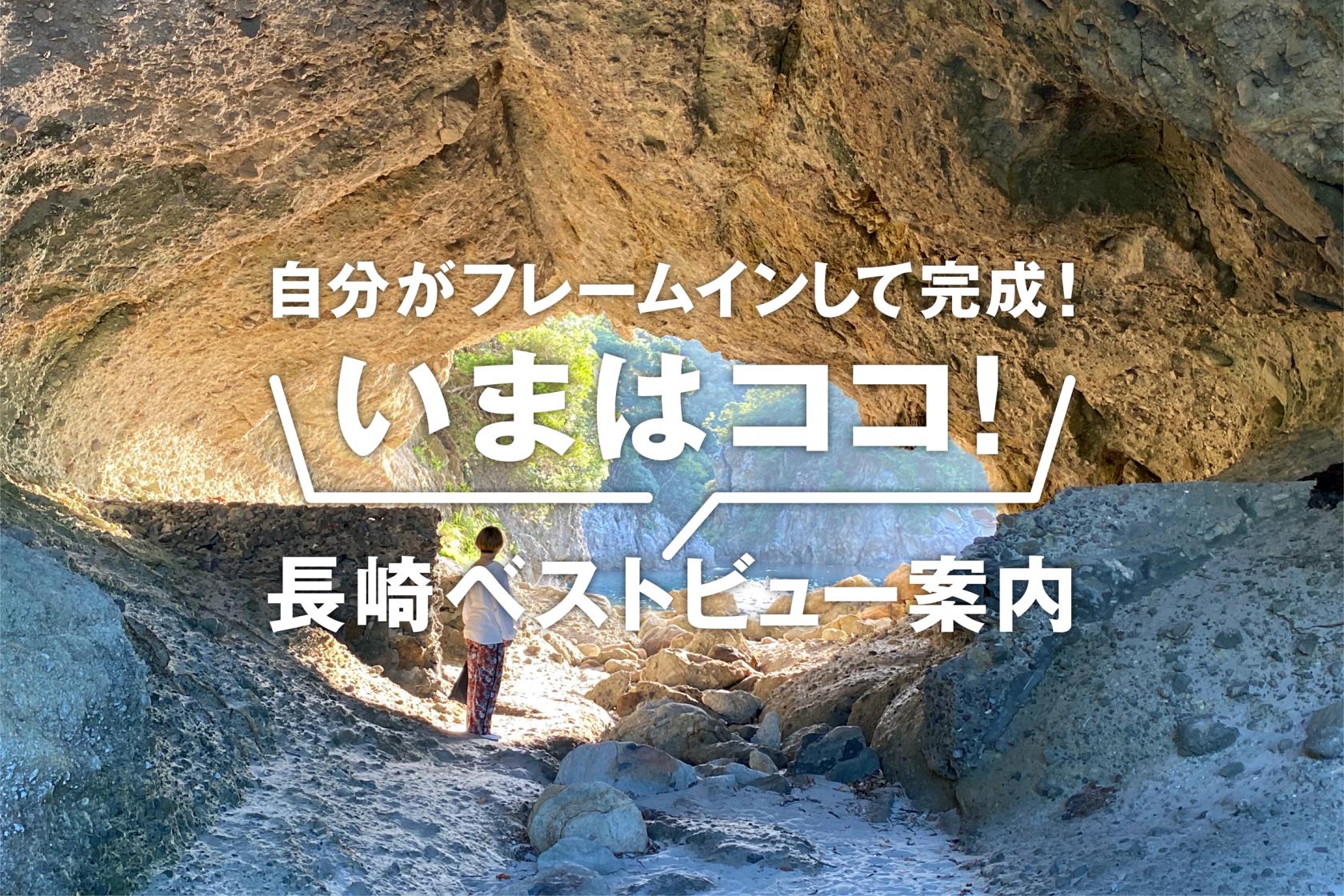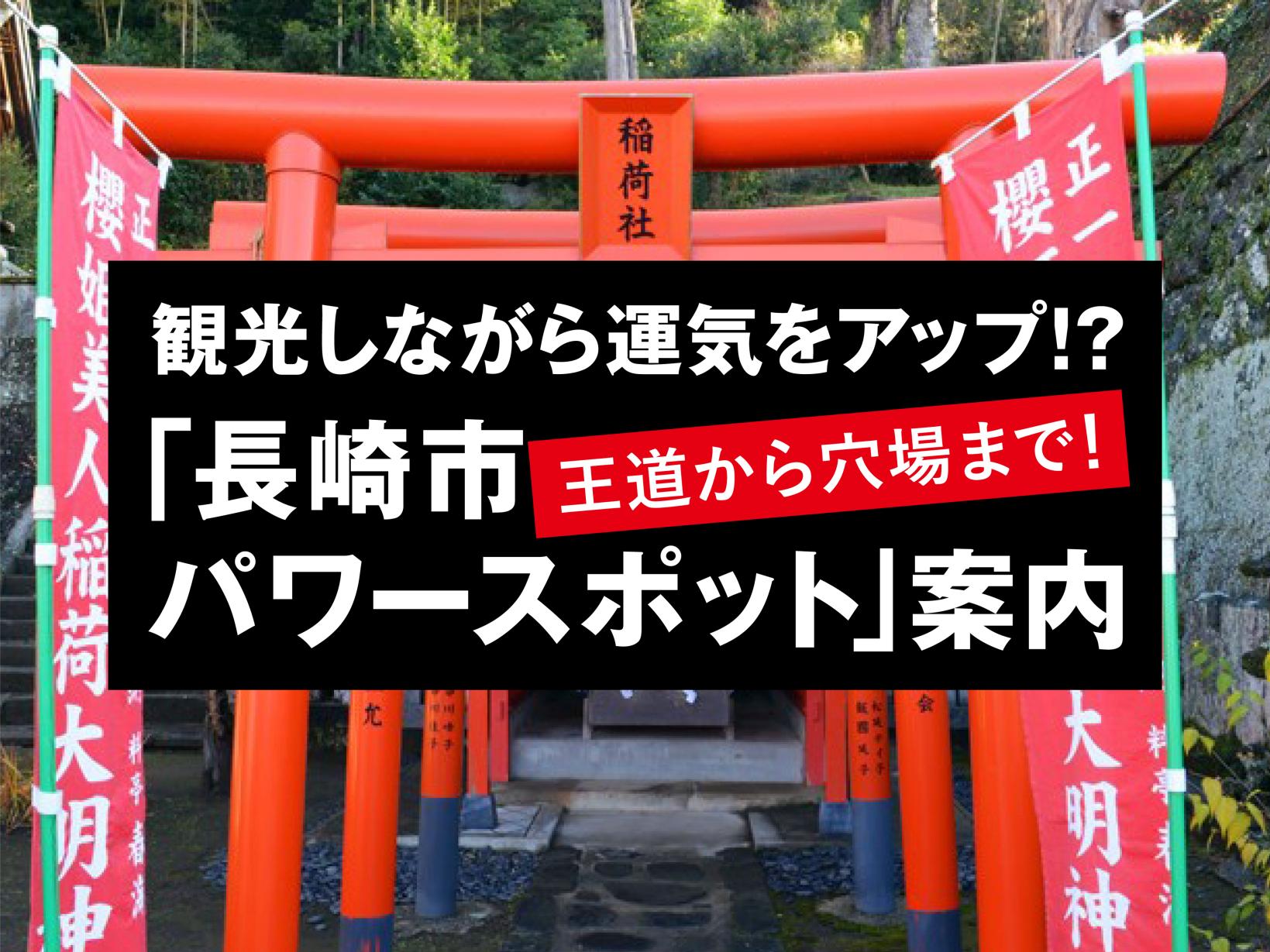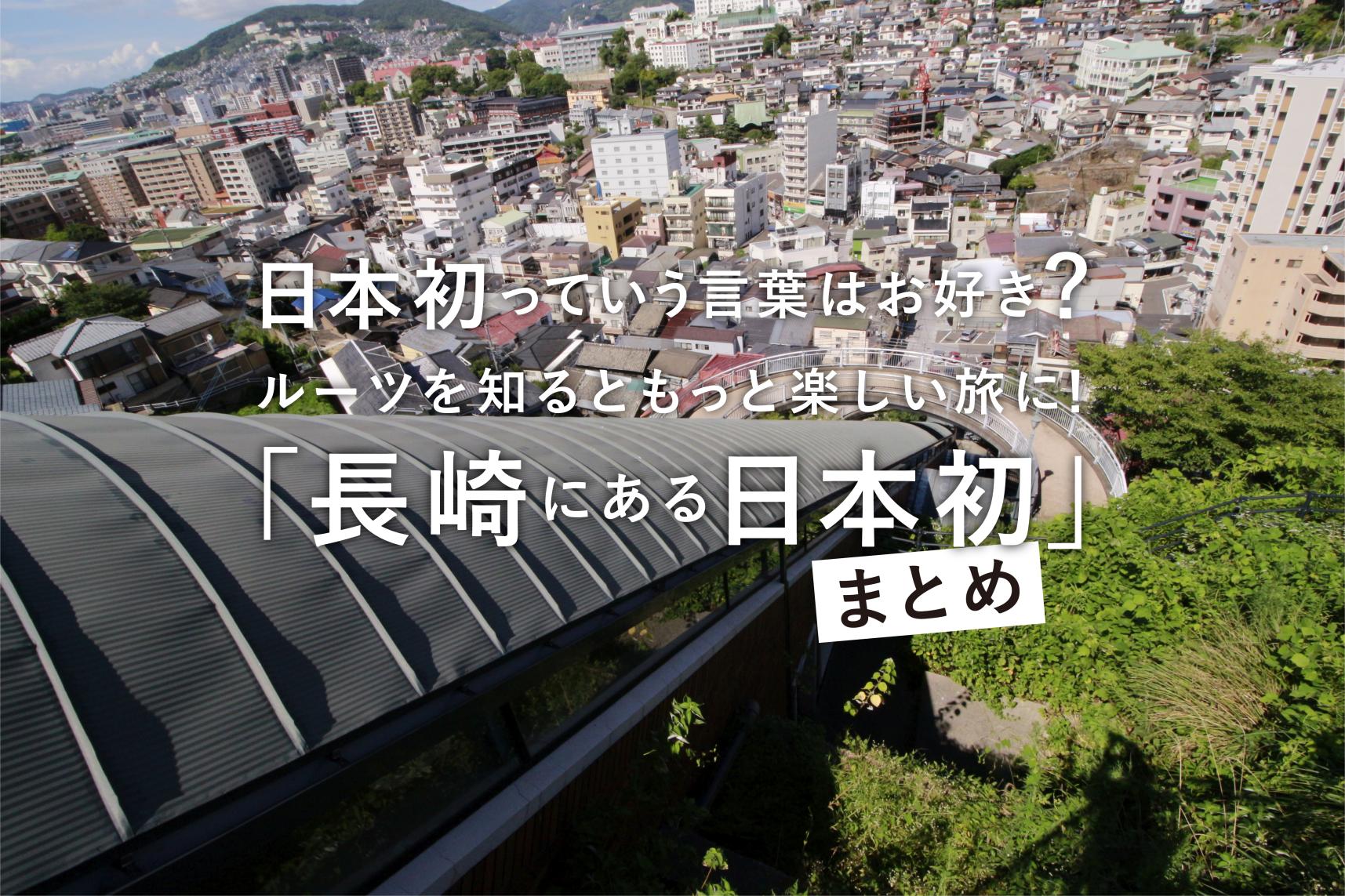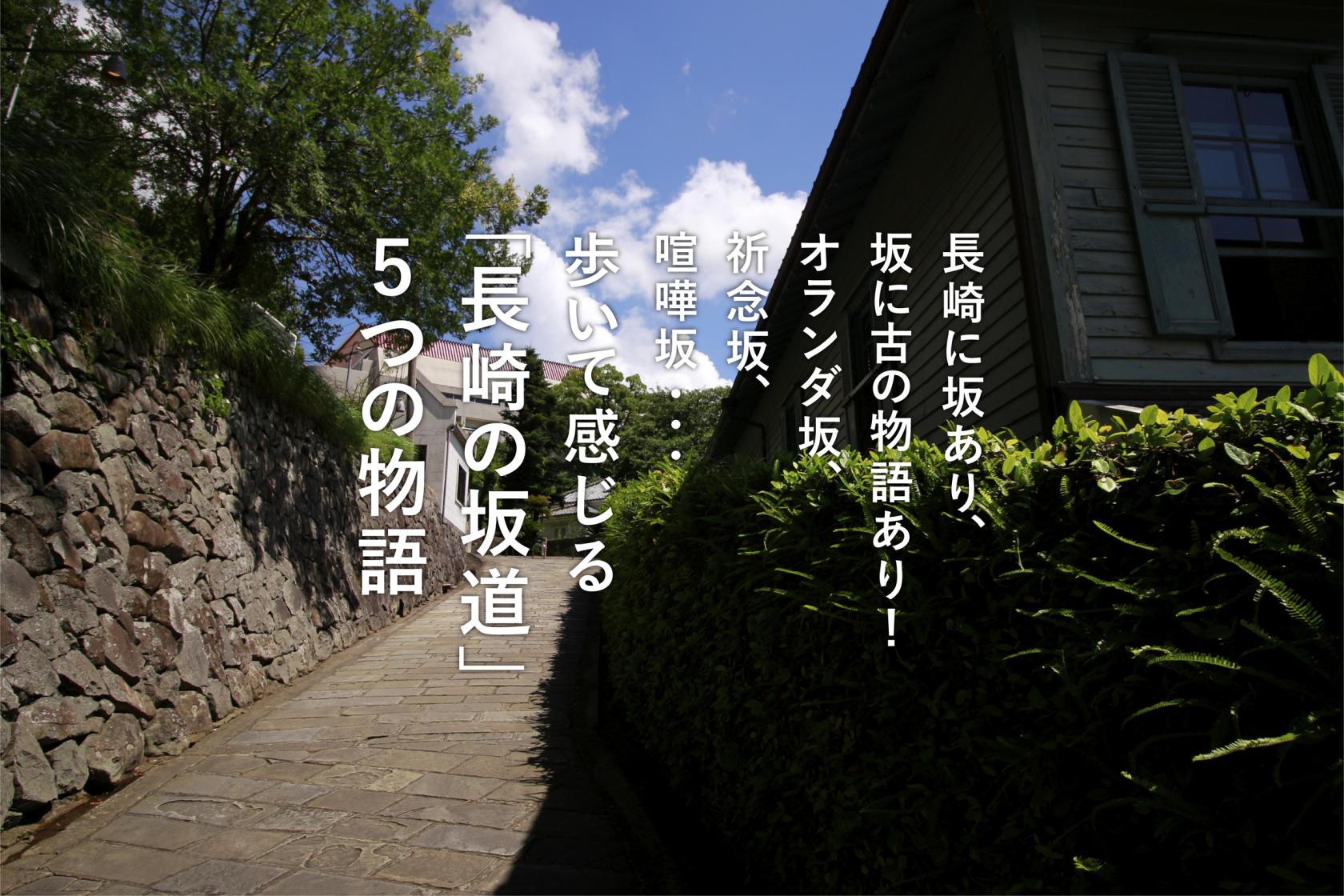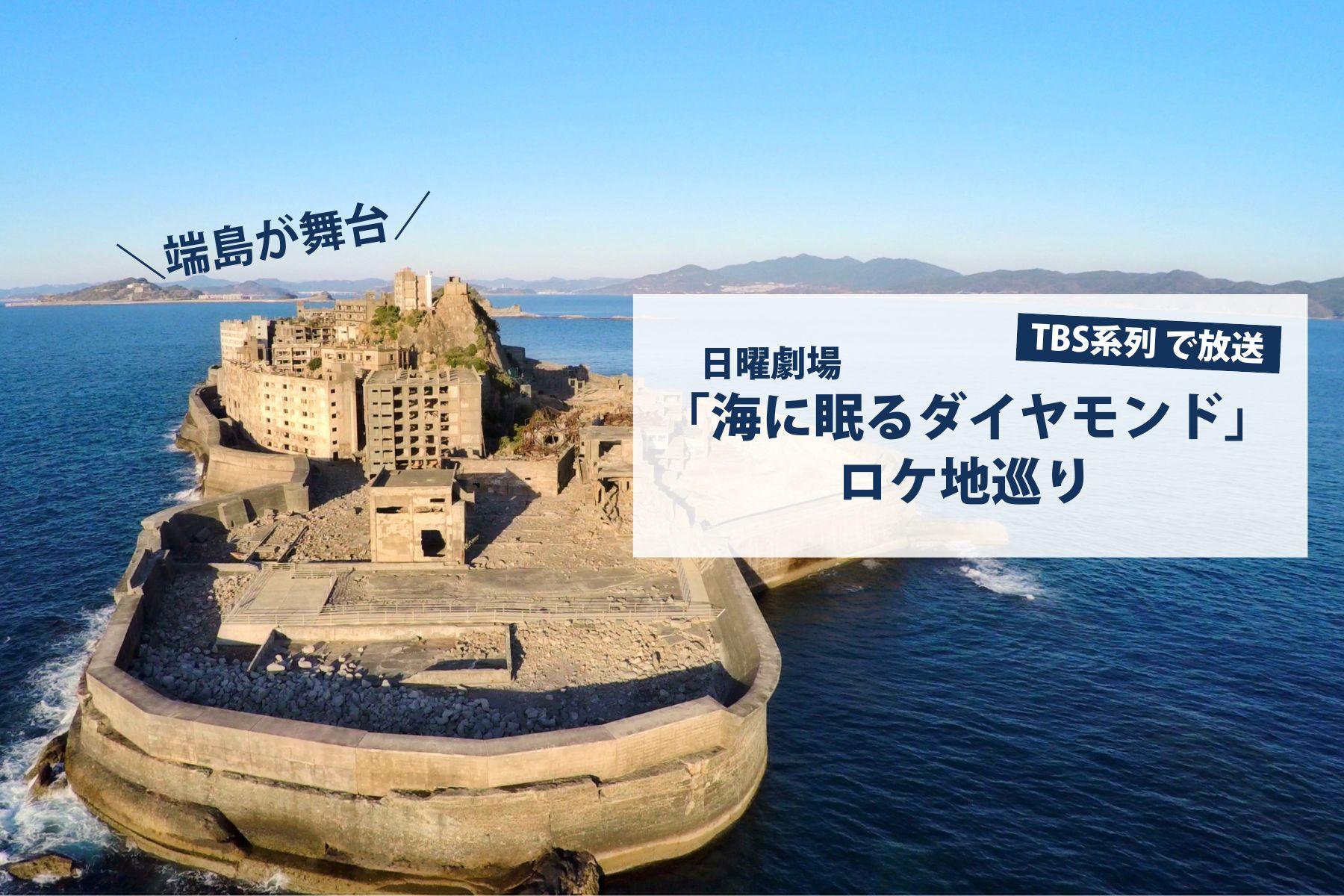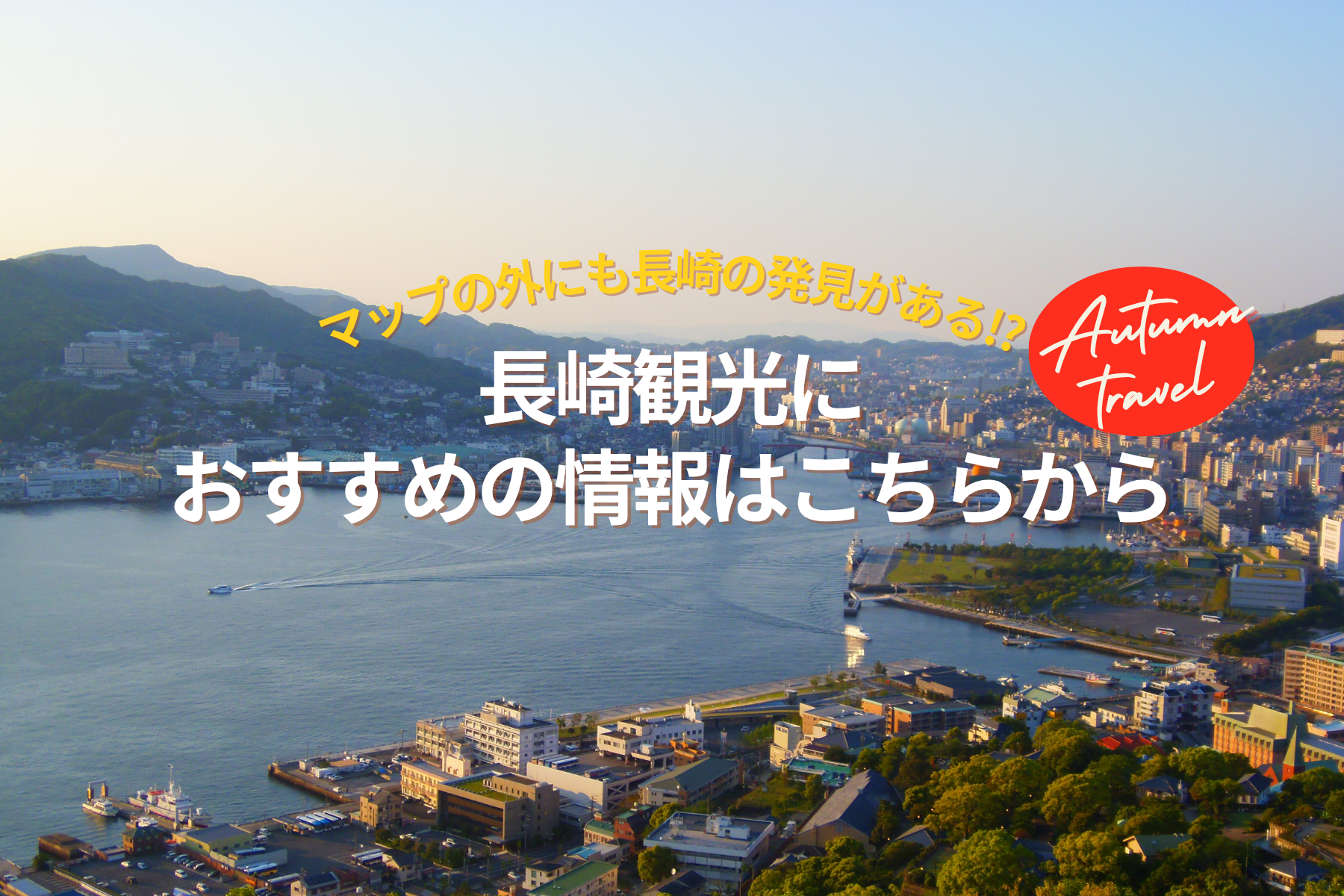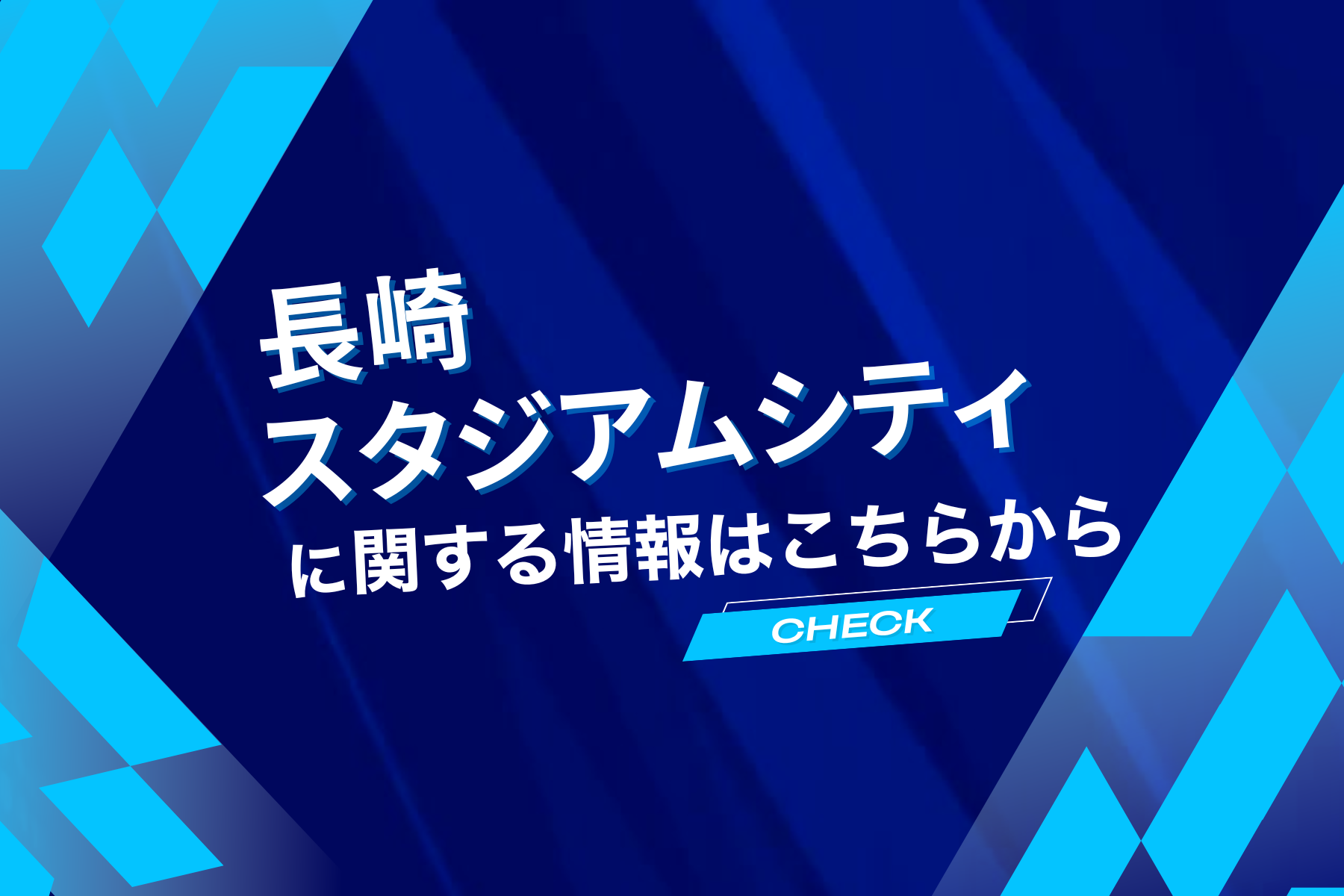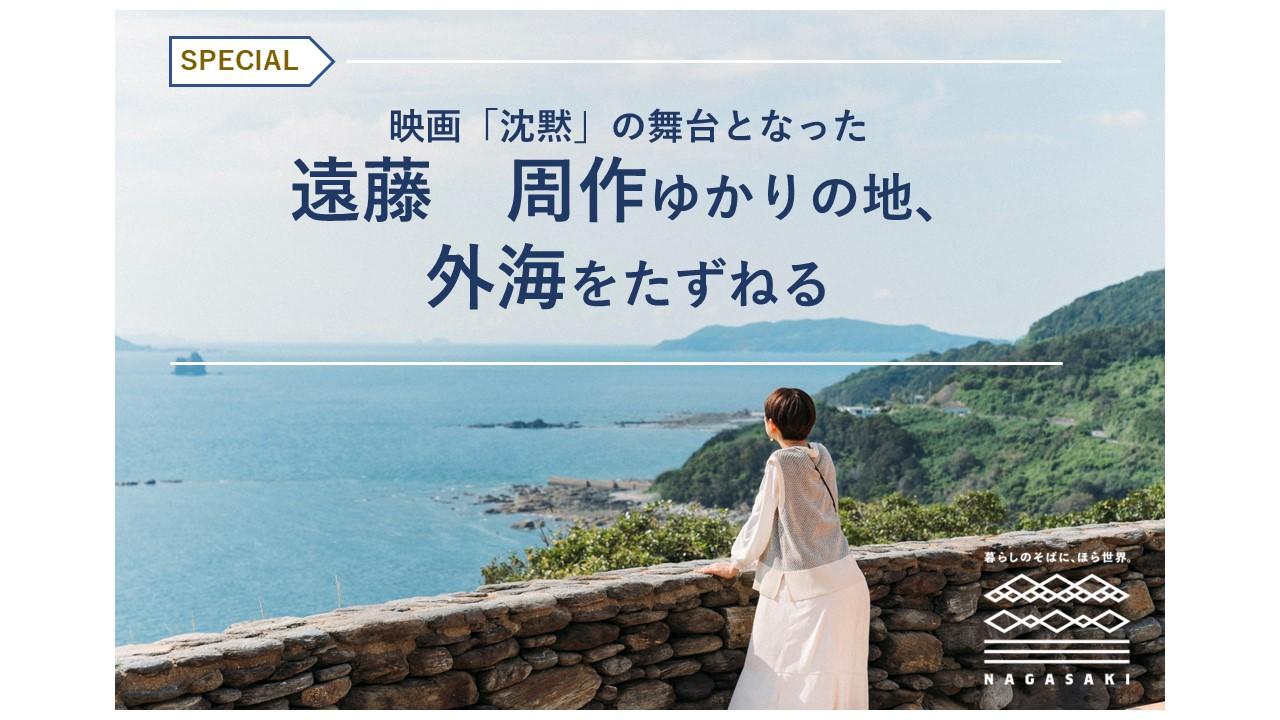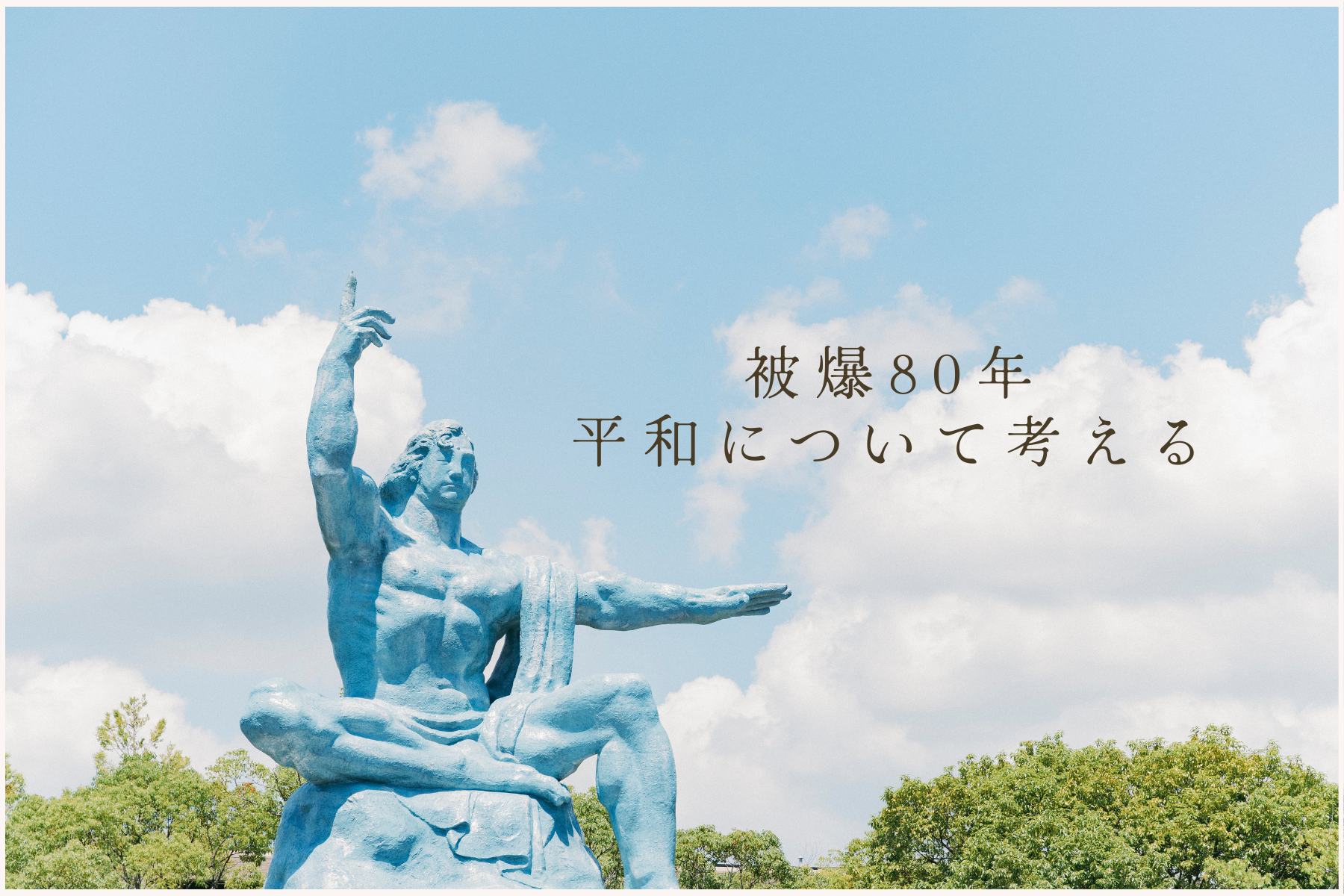#008 ながさきとべっ甲
#008 ながさきとべっ甲
⻑崎の海の宝⽯、べっ甲。本ページでは、⻑崎のべっ甲のストーリーから、スポット情報までご紹介します。
超絶技巧の造形アート べっ甲
【飴⾊の海の宝⽯ べっ甲】
べっ甲は、玳瑁 (タイマイ) というウミガメの甲羅を使って作られたもの。その透明感のある美しい飴⾊模様から“海の宝⽯”とも呼ばれています。その歴史は古く、奈良時代、遣隋使 ⼩野妹⼦が持ち
帰ったものが⽇本最古のべっ甲とされ、現在も奈良の東⼤寺正倉院に保管されています。江⼾時代、べっ甲の原料が⽇本に輸⼊されるようになったことで、⻑崎べっ甲の⽂化は花を咲かせました。当時、貿易都市として外国船の出⼊りが多かった⻑崎では、外国⼈船⻑から帆船模型の注⽂が続いたことで、アクセサリーに限らない、⿓や鯉などの精巧な美術品をつくる⼯芸技術が研鑽されたと⾔われています。
【⽔と熱の芸術 べっ甲細⼯】
べっ甲細⼯は、“⽔と熱の芸術”という呼び名のとおり、接着剤を⼀切使わずに、⽔と熱と圧縮によって甲羅を接着し、造形していきます。まずは図案を元に、製品に合う⾊や模様の甲羅を選び取り、型を当てて切り出していきます。数枚重ねて厚みを出すときは、表⾯をなめらかにして重ね合わせ、板状のものは万⼒で、⽴体的で曲線のあるものは押しごてで熱を加えて接着、かんざしなどの反っ
ている製品は、熱湯で煮て柔らかくしてから⽊型でプレスするなど、製品に合った道具を使って、精密な熱加減で加⼯を⾏います。おおまかな形が整ったあとは、⼿作業のレリーフ彫刻、サンドペーパーや布製摩擦機バフで丁寧に磨き上げることで、美しい装飾とツヤのべっ甲細⼯が完成します。
名品⽬⽩押し!⻑崎市べっ甲⼯芸館
【異国情緒豊かな 海辺のべっ甲ミュージアム】
⻑崎市べっ甲⼯芸館は、1898 年に竣⼯した国指定重要⽂化財 旧⻑崎税関下り松派出所を利⽤した伝統⼯芸品 ⻑崎べっ甲のミュージアムで、明治時代の異国情緒豊かな外観は、⻑崎市旧⾹港上海銀
⾏⻑崎⽀店記念館とともに、⼤浦海岸通りの象徴的な景観を作り出しています。館内では、歴史と伝統に培われたべっ甲細⼯の技術を保存するため、社団法⼈⽇本べっ甲協会から寄贈を受けた貴重な作品のうち、貿易船、鯉、鷲、電話機などのべっ甲細⼯の名品約300 点がずらりと展⽰されています。
美しくあるために そう呼ばれた「べっ甲」
⻑崎の花街丸⼭が描かれた⽊版画では、べっ甲細⼯の装飾品で豪華に着飾った遊⼥を⾒ることがしばしばあります。実は、べっ甲細⼯の正式名称は、「玳瑁細⼯」。本来、べっ甲とはスッポンや泥⻲のことを指します。江⼾時代、贅沢を禁じる奢侈禁⽌令が発されたとき、贅沢品である玳瑁製の⾼価な櫛やかんざしを守るために、価値の低いべっ甲製と⾔い逃れたことで、「べっ甲」の呼び名が⼀般的になったと⾔われています。べっ甲とは、役⼈の⽬をかいくぐってまで、おしゃれに着飾りたいという⼈々の知恵によって⽣み出された⾔葉なのです。

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)