-

東山手「地球館」café slow
国際交流と地域・観光の新拠点~坂の途中で、ゆっくり・のんびり~
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

大浦天主堂
国宝
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧グラバー住宅
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧長崎英国領事館
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

東山手洋風住宅群(7棟)
市指定有形文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧香港上海銀行長崎支店
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-
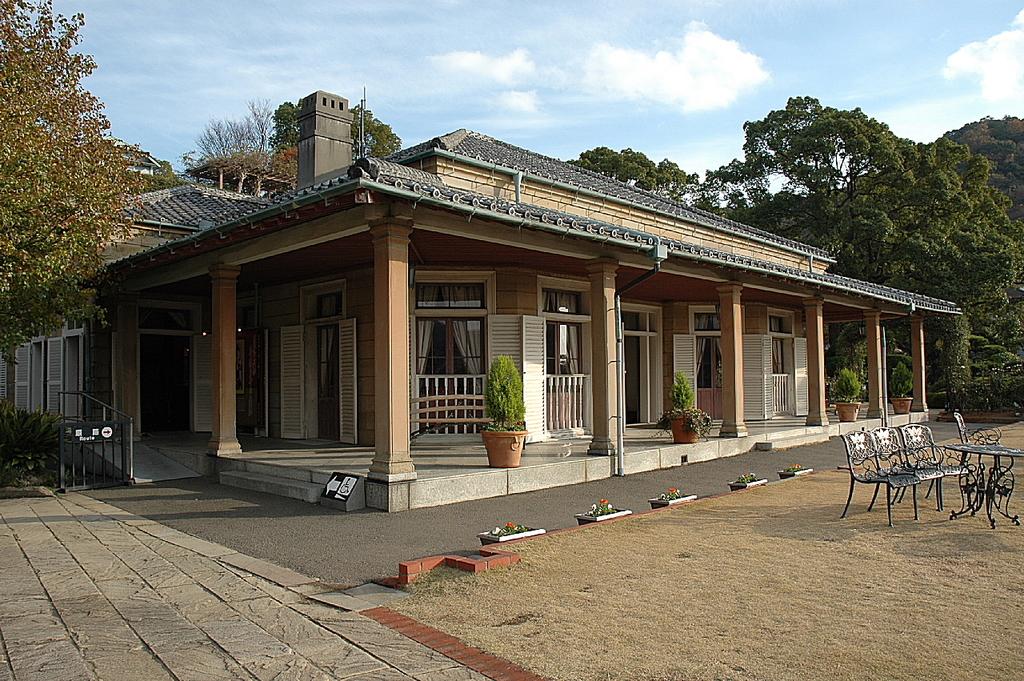
旧リンガー住宅
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧オルト住宅
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧長崎税関下り松派出所
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

大浦天主堂境内
国指定史跡
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

グラバー家墓地
市指定史跡
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

長崎市南山手伝統的建造物群保存地区
国選定重要伝統的建造物群保存地区
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧長崎大司教館
県指定有形文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

旧羅典神学校
国指定重要文化財
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
-

長崎市東山手伝統的建造物群保存地区
国選定重要伝統的建造物群保存地区
長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)
![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)
